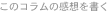第59回:死んでいく言語
更新日2008/05/08
言葉の話をさせてください。
毎週、このコラムに書こうと思い溜め込んでいるテーマはたくさんあるのですが、どうにもうまくまとめたり、話題を展開させることが難しい時には、専門の言語学関係の話題に逃げることにしています。と言うわけで、今回は世界から消えて行っている言葉の話です。
アメリカインディアンの言葉を研究している日本人の言語学者はとても多く、優れた業績をたくさん残しています。その言葉を話せる人は年取ったおばあさん一人だけになってしまったような言語を、おばあさんに何度もインタビューし、録音し記録するような、一見、今の目まぐるしく変わる世の中で、実利的な価値がない研究に生涯打ち込んでいる人が何人もいます。
一つの言語が消滅することは、一つの再生不可能な文化が失われることで、それが取り分け書き言葉を持たない文化の場合には決定的な喪失になります。最後のおばあさんが死んでしまったら、もう誰もその文化を知ることができなくなってしまうのです。
絶滅に瀕している動物を救う運動があるのと同じように、消えてなくなる言語を記録する研究も細々とですが存在しています。今、全世界で話されている言葉は5,000から、多く言う学者で6,809あると言われています。ですが、そのうちのたった100の言葉が世界の人口の95%の人によって話されています。言い換えれば、世界人口の5%の人が、6,000以上の違った言語を話していることになります。
そして、これからの100年間に、少なく見積もる人で半分、悲観的な人で90%の言語が消えて行ってしまうと言われています。復元不可能な言葉、文化が無になってしまうのです。
身近なところで、北米の太平洋岸に住むKtunaxa語を話す人は10人、 Siletz Dee-ni語は5人、
South Haida語も約10人しか生き残っていません。アメリカ中西部のWichita語に到っては3人だけしかいないのです。
南米の高原に住んでいたインディオの言葉も絶滅しつつあります。Taushiro語とUru語に到ってはたった一人づつしか話せる人がいないのです。言語はコミュニケーションの手段ですから、たった一人で話す相手がいないことは、すでに絶滅していると言ってよいでしょう。Muniche語を話せる人はまだ5人います。
日本に近いとところでは、サハリン、カムチャッカから東シベリアに住んでいるMendny Aleut語とOrok語を話す人は20人ほどしかいませんし、
Tundra Yukaghir語でも50人程度です。
なぜ消滅しつつある言葉を記録することが大切なのかは、絶滅に瀕している動物、生物をなぜ守る必要があるのかに似ています。直接的な利益にあまり関係ないように見える、そんな小さな生命がニ度と地球上に存在しなくなると、私たちの生活の豊かさが一つ消えて行ってしまうと思うのです。
日本オオカミが居なくなってからもう久しくなりますが、いかに人間が日本オオカミを絶滅に追い込んだかは別にして、もしまだ日本オオカミがどこかに生き延びていたら、深い山の自然がどれだけ豊かになるでしょう。想像するだけでもロマンを呼びます。
言語も日本オオカミと同じ生き物なのです。万が一、日本語が英語や中国語に侵略され絶滅したと想像してみてください。どれだけ多くの貴重な文化が一挙に失われてしまうことでしょう。
自分の文化を知るには、他の文化と比較すると多面鏡のように、今まで見えなかった部分を照らし出してくれ、一見、何の関係もなさそうな遠い国の少数民族の話す言葉、文化を知ることで、私たちの思考様式をより明確にすることができるという学者もいます。
観光客を呼び集めるような巨大な遺跡や、書き言葉による伝承文学を残さなかったとはいえ、何千何万もの部族は独自のやり方で自然とかかわってきたことでしょうし、その土地に根ざした信仰を持ち生活してきたことでしょう。人間の豊かさは自分の生活圏とはかけ離れたそんな文化がどこかに存在することで成り立っている…と信じています。
 第60回:アメリカの貧富の差
第60回:アメリカの貧富の差