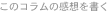第61回:アメリカの母の日
更新日2008/05/22
5月11日は母の日でした。日本ではどういう理由からでしょうか、カーネーションをお母さんに贈る習慣があるそうですが、一体どこから来た習慣かしら。
アメリカでもカードや花を贈ります。最近は少し大げさなくらい大きなプレゼントを贈る人が多くなってきました。普段の親不孝をこの日、一日だけで償おうというのは、日本もアメリカも変わりないようです。
私の母親もダンナさんの母親も健在です。なにもプレゼントなどはしませんが、毎年電話し、「母の日、おめでとう!」と、ご機嫌を伺うのが習慣になっています。
私の母はとてもシャープな人で、反応も決断も素早く、非常に優れた事務能力、組織能力があり、その上、向学心も強く50歳を過ぎてから、夜間と週末の大学院のコースを取り始め、5年かけて修士号を取ったほどです。写真のような記憶力の持ち主で、職場では彼女がいればコンピューターのメモリーなぞ必要ないとまで言われていたほどでした。
でした、と過去形で書いたのは、5、6年前から物忘れが酷くなり、電話口でも同じことを何度も繰り返したり、次の言葉が出てこなかったり、日常生活で毎日使っているもの、たとえばコーヒーカップをどこかとんでもないところにしまい込み、全く思い出せなかったりし始めたのです。それでも本人は、小さな脳溢血のせいにしていました。周囲の勧めで、ただ安心のためだけにでも…とアルツハイマー(英語の発音ではアールツアイマーなんですが…)の検診を受けたところ、やはり立派なアルツハイマーと診断されたのです。
まだ病状に山あり谷ありの状態ですから、普通の状態に戻った時、かえって自分が持っていた頭脳が壊れていく現実に直面しなければならず、彼女を打ちのめしています。私たちが外から見ると、ズーッとボケっぱなしの方が本人にとって幸せかなと、無責任に思ったりします。
できる限り機会を作っては実家に帰ったり、彼らを私たちの家に呼んだりしています。ウチでは母と私のダンナさんが早起き組みで、ニ人だけが大のコーヒー党です。私がまだベッドにいるうちに、コーヒーを煎れ、ニ人で朝を楽しんでいるようです。
朝型でない私が、珍しく早くにベッドを抜け出し、コーヒー党のニ人がいる台所のテーブルに近づいたとき、私のダンナさんが珍しくハッキリした口調で(普段はモソモソした言い方でしか話をしない人なんですが)、母にアルツハイマーだという現実を正面から受け止めること。これは人間が患うたくさんの病気の一つで、私たちにこの病気ならいいけど、あの病気は嫌だというような選択の余地はないこと、母が今まで異常な勇気を持ってアルツハイマーに立ち向かってきたことは彼に深い感銘を与えたこと、そしてこれから母にできることは、病状の進行を遅くさせるため、できる限り行動的な毎日を過ごし、人にどう思われているかを気にせず、馬鹿な失敗を犯すことを恐れないこと、そして何か失敗しても、自分を笑うユーモアの精神を持つこと、などなど話していたのです。
私たちの家族の間では、母の前でアルツハイマーという言葉を使うのさえ極力避けていました。万が一、話題になっても、「お母さん、アルツハイマーと言ってもまだまだ初期段階だから、普通の人でお母さんより物忘れが酷い人はたくさんいるよ」というような慰め方をしていました。私のダンナさんのように、「あなたはアルツハイマーであり、同じ状態が続くことはあってもよくなることはない」という現実をお母さんに正面から言う人はいませんでした。
母はとても気の強い人ですから、人前で涙を見せるようなことはありませんでしたし、私も一度も母の涙を見たことがありません。でも、驚いたことに、母がウチのダンナさんの前では崩れるように泣き、そのことを気にしている様子が全くないのです。それだけ彼に気を許しているのでしょう。
私はダンナさんの知らなかった一面を見ると同時に、それ以上に私の母に対する思いやりに深く感謝しました。そして、このダンナなら私がアルツハイマーでも、どんな病気になって倒れても、うまく私の世話をしてくれるのではないかと妙な安心感を持ちました。
でも、順番でいくと、10歳以上年上のダンナの方が私より先にヒックリカエル可能性の方がはるかに高く、そうなった時、私はどんな態度で接したら良いのか分かりません。
 第62回:アメリカの卒業式
第62回:アメリカの卒業式