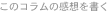第92回:師走とヘンデルの救世主「メサイア」
更新日2008/12/25
アメリカで一番大きな祭日はなんといってもクリスマスです。子供たちだけでなく、大人もクリスマスムードに染まってきます。スパーマーケットやショッピングモールの前で救世軍の人たちが寒さのなか、ゴロゴロに重ね着をしてベルを振り、義援金を集めている姿もクリスマス前の風物です。
クリスマスの音楽といえば、毎年、毎年同じ曲が繰り返されます。「きよしこの夜」「ジングル・ベル」「ホワイト・クリスマス」「赤鼻のトナカイ」それに賛美歌では「諸人こぞりて」などなど、決まりきった定番ばかりが繰り返されているのに不思議と飽きません。年一度だけ聞くせいでしょうか、それとも子供の頃からしばしば耳にしていた郷愁のせいなのでしょうか。一昔前ですと、ポップシンガーもカントリーシンガーもジャズ、ロックの歌手もオペラ歌手も、こぞってクリスマス・アルバムを出したものです。
日本でクリスマス、年末そしてお正月を何度か過ごしました。一年の区切りがどこかにあり、それをその国の伝統に従って過ごすのは、なにか安らぎを抱かせます。
すっかり日本の年末行事になってしまったベートーベンの「第九交響曲」は一体誰が始めたのかしら。ヨーロッパにもアメリカにもない年中行事ですが、第九交響曲は年を締めるのにふさわしい響きがあり、大合唱が終わると、ああこれで今年も無事に過ごしたという感慨が湧いてくるから不思議です。
ヨーロッパやアメリカでは第九交響曲は演出にお金がかかりすぎるためでしょうか、大指揮者が有名なオーケストラを指揮し、特別な機会にしか演奏しないと聞いています。日本ではどんな地方都市の小編成のオーケストラでも、若い指揮者がタクトを振り、アマチュアの合唱団が加わって、誰でも楽しめる第九を演奏しているようです。
先週、ヘンデルの救世主"メサイア"「シング・アロング(一緒に歌おう)・コンサート」に行ってきました。シング・アロングというのは客席の人が合唱部門を受け持ち、それぞれのパート、ソプラノ、メゾ、アルト、テェナー、バスと分かれて席に着き、正面のステージに陣取ったオーケストラと競演するものです。
クリスマス前になると大変な数のヘンデルの「メサイア」が歌われ、演奏されます。もともと英語で歌詞が書かれているうえ、例の有名なハレルヤ・コーラスが入っているので、英語圏のクリスマスでは抜群の人気、ヒットチャート・ナンバーワンの曲になっています。バッハのクリスマス・オラトリオなどは完全に無視された感じです。
私の住んでいる田舎町には、メサイア協会というのがあり、ボランティア、アマチュア、セミプロ、音楽教師のバイオリニスト、フルーティスト、チェリストらがオーケストラのパートを春頃から練習し、4人のセミプロと呼ぶべきか、上手なアマチュアと呼ぶべきか、その境界線にいる声楽家を招き、独唱部を受け持ってもらい、合唱は私のような素人がいきなりぶっつけ本番で唄います。
メサイア全曲の楽譜は分厚いものなので、その中からよく知られた部分だけを演奏しますが、それでも15分の休憩を挟んで、2時間以上かかります。
唄いに来ている人は、やはり年配の人が多く、ヨレヨレのおじいちゃん、おばあちゃんの姿もあり、古本屋さんでもなかなか見つからないような古い楽譜を広げていたおばあさんがいたので、訊いたところ、1912年出版の希少本でした。彼女も希少本のような存在の歳でした。
難しい曲では急に合唱の音量が減り、誰でも知っているパートになると盛大な合唱になるのはしかたがありません。
下手なアマチアオーケストラに全くの素人の合唱でも、こんな参加型のコンサートは楽しく、唄い終わった後で、周りにいた人々に、「良いクリスマスを!」と挨拶しあって家路につく時、ああ今年もまたクリスマス・シーズンになったなーとしみじみ思います。
 第93回:現代人の衰えていく嗅覚
第93回:現代人の衰えていく嗅覚