|
第45回:バスク語と日本語、そしてスペイン語
スペインでは、バスク語(vasco:バスコ)*のことを悪魔が作った言葉、複雑怪奇で習得不可能な言葉と言われ、訳の分からないことを言っていると、“バスコでなくカスティジャーノで話せ!”と諭される。
ポルトガル人が初めて日本に流れ着き、それからフランシスコ・ザビエル(彼自身がバスク人だった)、カトリックの坊さんたち、主にイエズス会の坊さんが日本で過激な布教を始めた頃、早い時期に簡単な日本語=ポルトガル語の辞書を作っている。しかし、彼らが総本山のバチカンに宛てた手紙で、“日本語は悪魔が作った言葉のようだ…”と、不可解な言葉に接した時の常套句を使って、日本語の難しさを訴えている。
このイビサ物語の中で、私が流暢なスペイン語を操り、スペイン人とのコミュニケーションに全く問題がない…ような印象を与えているなら、ここで大きく訂正しなければならない。私のスペイン語はどうにかかろうじて疎通が成り立つ程度で、しかも動詞の変化をかなり無視した間違いだらけの代物なのだ。
スペイン語をきちんと勉強したこともなければ、スペインに来てからも外国人向けの語学学校にすら通ったことがない。マドリッドの中心、プラサ・マジョールのカフェテリアにたむろしていたデパートの店員や女工たちと同席し、覚えたての単語を連発し、コミュニケーションを図っていただけで、かなり多くの人の手を経てNHKのスペイン語講座のテキストが回ってきてから、午前中はそのテキストに沿い、一章づつ自習し、その日の午後に即、若いセニョリータたちを相手に実践する、という遣り方で覚えたスペイン語だから、お里が知れているのだ。
少しだけスペイン語の日常会話ができるようになり、半分も意味が分からないながらも新聞や雑誌を広げるようになってから、一つの言葉を習得するというのは、言語活動だけでなく、文化そのものを体現しなければならないと、当たり前のことを思い知ったのだった。
そして、一つの言語をマスターするという表現には、大きな開き、曖昧さがあり、旅行会話程度から、古典や硬派の論評を読みこなせ、かつ書け、その国の一流の学者、政治家と討論できるレベルまでの差があるのだ。
プラサ・マジョールでの私の先生、セニョリータたちには大いに感謝するが、彼女らはおそらく一冊の古典も読んだことがなく、雑誌もカラーグラビアばかりの低俗雑誌しか読んでいなかったと思う。私のスペイン語の先生たちはそんなレベルだった。

Plaza Mayor, Madrid
スペイン語には、日本人にとってとっつき易い面がある。発音が明確なのだ。書かれたスペイン語を意味が分からないにしろ、幾つかの読み方、発音のルールを知るだけで、どうにか声を出して読むことができるのだ。これが英語だと、すべての単語をどう発音するのか、いちいち覚えなくてはならない。
もう一つ、スペイン語圏で実地にスペイン語で会話する大きなアドバンテージは、彼らがこっちの片言以下のスペイン語を一生懸命に聴いてくれることだ。そして、当方が分かる、分からないにかかわらず、彼らは大声で何度でも繰り返し話してくれることだ。
時に顔を近づけ過ぎ、唾がかかることもあるが、「エンティエンデス? コンプレンデス?(entiendes? comprendes?;分かったか、理解したか)」と、当方が「シー(si;はい)」と答えるまで、時にはしつこいほど押しまくられるのだ。これが英語圏なら、“何だコイツは英語も話せないのか…”と会話を打ち切られ、こちらのヨチヨチ英語を聞こうともしないだろう。
生徒の私にしても、ハナからスペイン語の古典を読みこなし、新聞の論説を理解し、スペイン語でモノを書くことなど目指していない、場当たり的な生徒だった。
スペイン語の動詞には“-ar/-er/-ir”の基本形があり、語尾がそれぞれ直説法、接続法、命令法などと様々に変化し、それに現在、点過去、線過去、未来、過去未来、など16の時制が加わり、しかも主語、単数・複数によってさらに変化し、しかも二人称には尊称と蔑称があるのだ。直説法点過去形や接続法未来完了形を二人称尊称を主語にした場合……となると、これぞ悪魔が故意に複雑怪奇に作ったとしか思えないのだ。
例えば“vivir (ビビール;生きる) ”という動詞は64にも変化する。それでさえ“vivir”は“-ir”規則動詞だが、他に不規則動詞があり、それらは一々奇妙奇天烈な変化をするのだ。ここに到って、私は開き直り、“俺のスペイン語はストリート・スペイン語で良い、日常的な雑用が足せればそれで良い、自称、カタコト・スペイン語の大家でヨシ”としたのだった。もちろん、自分には語学の才がなく、勤勉な学習者でないことを棚に上げてのことだが…。
私の極親しい日本人の友人は、スペイン人以上に巧みにスペイン語を操り、電話越しに彼が話すのを聞いたスペイン人は皆が皆、彼がスペイン人か、そうでなければ、スペインで育ったに違いない…と思い込むほどだ。そんな日本人が幾人もいるのだから、私が自分のスペイン語の拙さをスペイン語文法のせいにする訳にはいかないのは承知のうえだ。
確かに、動詞の変化を正確に使えば、モノゴトを的確に言い表すことができる。曖昧モコとしたアンビギュアス(ambiguous;不明瞭、あいまい)な表現を避けることができるのだろうな…とは想像できる。しかし、日本語を普通に話す私たちが、文法など知らずに、拘らずに会話し、読み、書いているように、スペイン人でもそんな文法に拘わってしゃべる人、書く人はまずいないのだ。
比較的均一化された日本の教育制度のためか、日本で育っていれば、文法的に大きな間違いを犯さずに日本語を書くことができるだろう。しかし、スペインには義務教育さえ満足に受けていない人が(その当時)相当数いた。彼らの書くスペイン語たるやスザマジイもので、スペルはデタラメで、文法も何もあったものではない。
洗い場のカルメン叔母さんもほとんど文盲だった。給料を渡す時、簡単な領収書にサインをして貰っていたが、自分の名前さえ、苦心惨憺の態で書いていたものだ。娘のアントニアは向学心が旺盛で、スペイン語の読み書きができ、シーズンオフの冬場には英語学校に通っていたが、彼女の十代の従兄弟二人は文盲に近かった。
アンダルシアの田舎者、ジプシーたち、マドリッド、バルセロナでも、下町育ちと高等教育を受けた人の言語能力のギャップは唖然とするくらい大きい。修辞、慣用句の多い公文書だけでなく、簡単な手紙にもその違いはハッキリと表れる。門外漢の私の目から見てさえ、その文章を書いた人の言語レベル、強いては知的レベルが容易に計れるほどだった。
今になって思うのだが、どうしてマジメにスペイン語を勉強しなかったのか、なぜイビセンコ(イビサ語)を学ぼうとしなかったのか、大きな悔いを残している自分に気が付くのだ。一つの言い訳だが、どうにか用が足りる程度に話せ、聞け、書けるようになると、その時点で、マー、これで良いかと怠け癖が出てしまったのだと思う。
このイビサ物語を読んで、私がいかにもスペイン語が達者だという印象を抱いたら、それは事実とは異なる。私は片言にほんの少し毛が生えた程度のスペイン語を操り、スペイン、イビサで十余年をも過ごしたのだ。
外国語を話すには、ある種のズウズウしさ、軽薄さが必要だとよく言われるが、その意味で、私はその軽薄さを人一倍持ち合わせていただけだ。そして、闇雲に行動に走る軽率さを引きずって今まで生きてきたような気がするのだ。
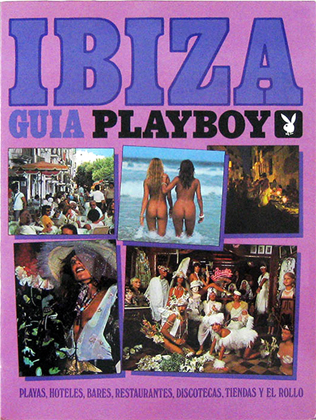
イビサガイドブック、Playboy Guia Ibiza:1979年刊
-…つづく
*バスク語:Vasco(Euskara):フランスとスペインにまたがるバスク地方の言語。言語人口は約66万人といわれ、ラテン文字で表記する。言語系統は不明で、現存する他の言語と関係性持たないいわゆる孤立言語。
 第46回:占い師マイオンと従者の青年 第46回:占い師マイオンと従者の青年
|



